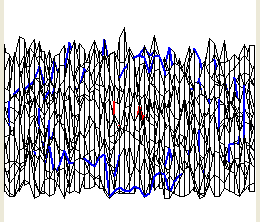
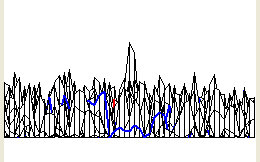
デフォルトの30度から見たところですが...ノイズが多く、星像がどれであるのか、よく見ないとわかりません。
グラフを回転させて、真横から見るようにすると...
ようやく、星像がつくるピークが見えてきました。
Aperture径設定の測定値への影響
初稿 2006.4.16
改訂 2006.4.21
1.はじめに
Aperture径を適切に設定することで、ノイズの影響を低減させることができます。
そのようすを、実際の測定で示します。用いた画像は、川村晶氏により観測された (141)Adeona による TYC2498-01243-1(mag10.4)の食の観測(2005年2月2日UTC) です。
2.画像のようす
画像は、10.4等の恒星の食を、「300mm F2.8」の35mmフィルム用カメラレンズを用いて、ビデオカメラで撮影したものです。小惑星による恒星食では目的星の導入に苦労することが多いですから、このように広い写野の確保できる光学系を使うことができれば、時間的な余裕のない時など、観測成功率が高まると期待されます。
この画像の場合、恒星の等級に対して小さめの口径(10.7cm)ですので、ビデオカメラのゲインを高く設定して撮影されています。そのために、ノイズが多い画像となっていますが、目的星は、画面上ではっきりと確認することができます。
画像の特徴を見るために、星像のようすを、Limovieの3Dグラフで表示させてみました。
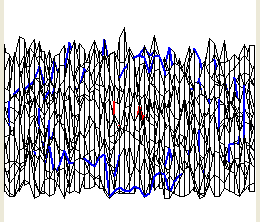 |
|
|
デフォルトの30度から見たところですが...ノイズが多く、星像がどれであるのか、よく見ないとわかりません。 |
グラフを回転させて、真横から見るようにすると... |
ノイズのつくるピークは、星像のピークの高さの半分以上に達しています。 このような画像から、どのような測定データが得られるでしょうか? Aperture径の設定を変えて、確かめてみましょう。 3.Aperture径の設定のしかた まず、Limovieの3Dグラフ機能を使って、Aperture径と星像の関係を見ます。
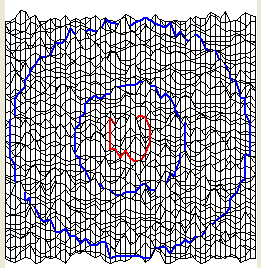 |
Aperture radius = 4
pixel
です。 |
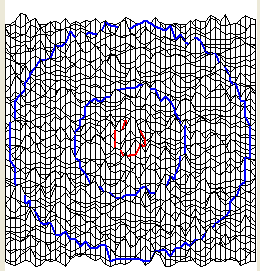 |
Aperture radius = 3
pixel
です。 |
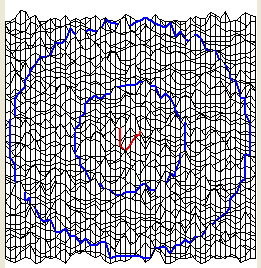 |
Aperture radius = 2
pixel
です。 |
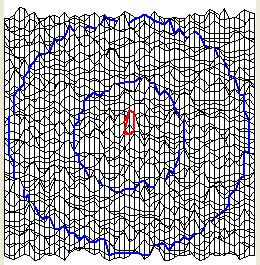 |
Aperture radius = 1
pixel
です。 |
4.Aperture径を変えた測光 実際の測光値について、径の大きい方から順にグラフを示します。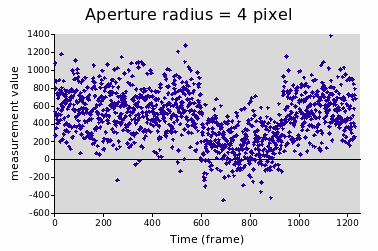
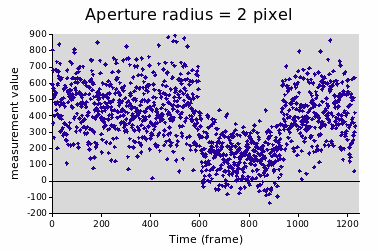
Apertureの径が星像よりわずかに小さい(Aperture radius=2)のときが、グラフがもっともまとまって表現されているように見えます。また、Aperture radius=3 の場合とはそれほど大きな違いはありません。更に、Aperture径を小さくしすぎると、データのばらつきが増えてしまいます。
註: Limovieの半径(radius)は、「円の中心となるピクセル」の中心と、「円周上のピクセル」の中心の距離により表現されています。したがって、半径=0 というのは、Apertureが一つのピクセルよりなることを示します。
5.現象時刻の推定
では、次に、画像表示ではわかりにくかった星像の消失の部分を詳しく見てみましょう。
現象前後の13.3秒間の測定値の変化です。
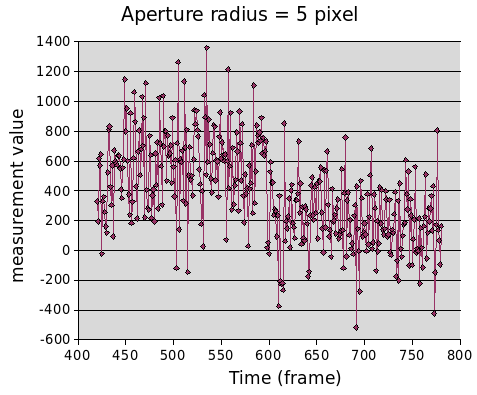
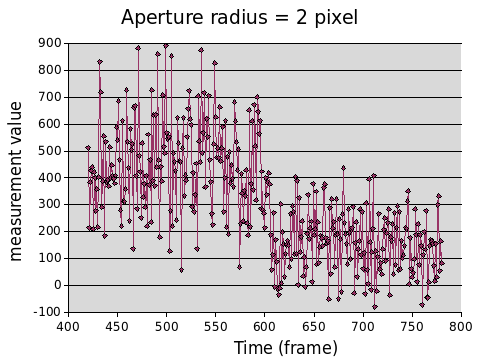
一見、両者とも消失前と消失後が分離されているように見えますが、radius=5pixelの場合は、消失前後の値が入り組んでいて、どこを消失としてよいのか、判断に迷います。一方、radius=2pixelの場合は、消失の前後をかなり明確に分けることができそうです。
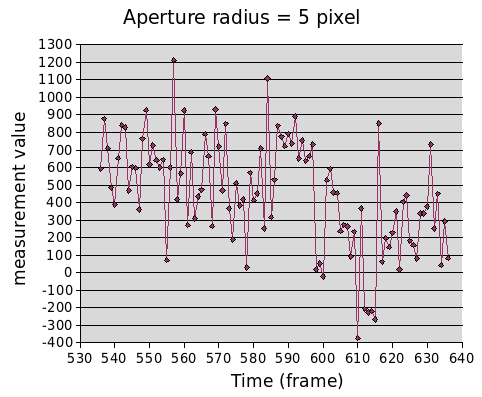
5pixelのグラフを更に拡大してみました。どこが消失時刻でしょう。597フレーム付近に0付近の数値でしょうか。それとも605フレーム付近? よくわかりません。
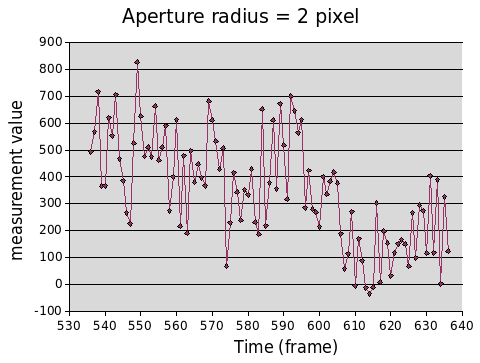
2pixelのグラフです。こちらは、細かい振動の状況から考えて、星像消失は606フレームでおこったと考えられます。606フレーム以前の振動成分をならしてみると、測定値の平均は200以上であると思われます。それに対して、606フレーム以降の平均は、200またはそれ以下です。606フレームがその境であることが読み取れます。
これをもとに実際のビデオ画像を観察すると、星像が606フレームで消失していることがわかりました。そこで、606フレームの画像からTIViの表示を読み取った結果、
現象時刻を、 2005年2月3日 4:58:35.22 sec と求めました。
註 画面の観察:
減光量がわずかでノイズが多い画像の場合、画面を見ても星像の消失や出現の判断に迷うことがあります。このようなときは、Limovieでグラフを作成し、消失したと考えられるフレームの範囲を特定します。その付近のフレームを、Limovieの表示した画像をコマ送りして観察します。観察のポイントは、
「星像は止まったままだが、ノイズは流れるようにして移動していく」
ように見えることです。慣れれば、画面の観察だけでも消失や出現を知ることができますが、Limovieを活用して数値化することにより、効率的に作業を進めることができ、客観的で確実な時刻推定ができます。
詳しくは、
をご覧ください。
6.まとめ
4(グラフの比較)にも書きましたが、再度まとめます。
Apertureの径が星像よりわずかに小さい(Aperture
radius=2)のときが、グラフがもっともまとまって表現されているように見えます。また、Aperture
radius=3 の場合とはそれほど大きな違いはありません。更に、Aperture径を小さくしすぎると、データのばらつきが増えてしまいます。
以上の結果は、Aperture径についておこなった考察とよく合っています。
Aperture径を最適に設定した測定値は、ノイズによると考えられる振幅が減少することから、現象時刻を高い確度をもって推定することが可能です。
ノイズの多い画像でも、Aperture径を 「星像と同じか、またはそれよりわずかに小さく設定する」 ことにより、良好なデータを得ることができることがわかりました。